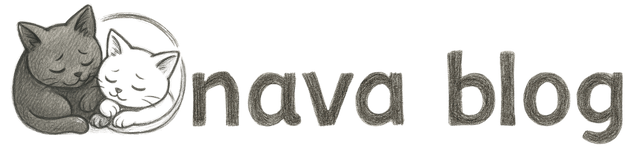泣き顔や怒りに、心まで揺れていませんか?
- 子どもが泣くと、自分の胸がギュッと苦しくなる
- 怒られている子どもを見ると、自分まで傷つく
- 感情に引き込まれて、しばらく気持ちが沈む
こんな風に、子どもの感情に強く引っ張られてしまうことはありませんか?
それ、あなたが冷たいわけでも、弱いわけでもありません。
HSP(Highly Sensitive Person:繊細な気質)さんは、共感力がとても高く、 他人の感情を“自分のこと”のように感じる性質があります。
特に子育て中は、
- 泣く、怒る、笑う、甘える…
- 子どもの感情が目まぐるしく変わり
そのたびに心が揺さぶられて、情緒が不安定になりやすいんです。
この記事では、
- 子どもの感情に共感しすぎて疲れる原因
- 自分を守るための共感ケア習慣
- 「子どもを大切にしながら、揺れない心を育てる」方法
をお届けします。
結論:共感しすぎる自分を、まずは“いたわる”こと
ぶっちゃけ、共感力が高いってとても素晴らしいことです。 でも、それが行きすぎると自分が感情の海に飲まれてしまいます。
子どもの気持ちに寄り添うことは大切。 でも同じくらい、「自分の心を守る」ことも大切です。
だからこそ必要なのは、
- 感情の境界線を引く
- 自分の気持ちを外に出して整理する
- 頑張った自分を意識的にねぎらう
この3ステップ。
共感しながらも、自分をすり減らさないための習慣を一緒に作っていきましょう。
子どもの感情に飲まれてしまう毎日
1. 子どもの涙に、心がもっていかれる

子どもが泣いたとき、
「私の声かけが悪かったのかな…」
「ちゃんと見てあげられなかったかも…」
そんなふうに、すぐ自分を責めてしまうことってありませんか?
僕もそうでした。
ちょっとしたケガや、子どもの失敗を見ただけで、なぜか自分まで落ち込んでしまうんですよね。
気づけば、自分の気分が子どもに左右されていることに気づいて、さらにモヤモヤ…。
でもそれって、決して弱さなんかじゃないんです。
HSP(繊細な気質)さんには、**「相手の変化にすぐ気づけるやさしさ」**があります。
「大丈夫?」「疲れてない?」って、空気を読む力がある。
でもその反面、感情を“受け取りすぎてしまう”こともあるんです。
子どもの悲しみや怒りに、まるで自分が包まれるように共鳴してしまう。
それだけ共感力が強いからこそ、感情の境界線がぼやけやすいんですよね。
まずは、「これは私の感情?それとも子どもの感情?」と、一歩引いて見ることから始めてみてください。
自分を守るための“やさしい線引き”、とても大切です。
2. 怒られる子どもを見ると、なぜか自分が傷つく
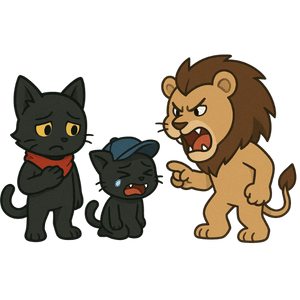
子どもが先生に注意されたとき、
まるで自分が怒られているような気持ちになったこと、ありませんか?
僕はあります。何度も。
他の親との会話でも、
ちょっとした一言に**「責められてるのかも…」**と感じて、モヤモヤが残ることも。
そして、子どもを叱ったあとには、
なぜか自分の心がずっと痛くて、ズーンと重たい。
これって、HSP(繊細な気質)さんに多い「共感性の強さ」が関係しています。
つまり、人の気持ちや空気を深く受け取るあまり、自分の心との“境界線”があいまいになってしまうんです。
- 怒られてないのに、怒られている気がする
- 責められてないのに、責められている気がする
- 子どもの感情が、そのまま自分の感情になる
そんな風に**「相手の感情が自分の中に入り込んでしまう」**感覚、すごくよくわかります。
これは性格の弱さじゃなくて、感受性の豊かさゆえの反応なんですよね。
共感しすぎるHSPさんの「心を守る習慣」
1. 「これは子どもの感情」と線引きするクセをつける
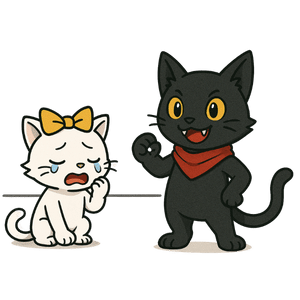
感情に“線を引く”だけで、心がグッとラクになる
子どもが泣いてるとき、
誰かにきつい言葉を言われたとき、
つい感情がグワッと入り込んでしまうこと、ありませんか?
HSP(繊細な気質)さんは共感力が高いぶん、相手の感情まで自分のことのように感じてしまうんですよね。
でも、それをずっと受け止め続けていると、心がどんどん疲弊していきます。
だからこそ大事なのが、「これは誰の感情?」と問い直すことなんです。
実際に僕がやって効果的だった方法をいくつか紹介します。
- 子どもが泣いていたら、「これはこの子の気持ち」と心の中でつぶやく
- 他人の言葉に反応しそうになったら、「今、私はどう感じてる?」と立ち止まってみる
- 紙に「子どもの感情」と「自分の感情」を線を引いて分けて書く
これ、ほんとに不思議なんですが、「分けて考える」だけで感情がスッと落ち着くんです。
大事なのは、“線引きすることは冷たさじゃない”ってこと。
むしろ、ちゃんと境界線を持つことで、自分も相手も丁寧に向き合えるようになるんですよね。
感情に巻き込まれそうになったら、まずは一歩引いて、「これは誰のもの?」と問いかけてみてください。
そのひと呼吸が、心のゆとりを取り戻す第一歩になります。ではなく、“やさしさを持続させる手段”です。
2. 感情を書き出して、客観視する
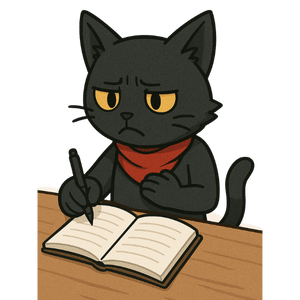
思考と感情は「書き出すだけ」でラクになる
HSP(繊細な気質)さんって、思考や感情が頭の中にずっと残りがちなんですよね。
「あのときの一言、気にしすぎかな…」
「なんであんなにモヤモヤしたんだろう」
こんなふうに、ぐるぐる思考が止まらなくなると、それだけで心が消耗してしまいます。
でも、それを防ぐシンプルな方法があります。
それが、**「書き出すこと」**です。
実際にやってみると、こんな気づきがあります。
- 「あ、これってただの思い込みかも」
- 「感情が反応してただけで、相手の意図じゃなかったな」
頭の中に渦巻いてたものが、文字になるだけで整理されるんですよね。
僕がやってるシンプルな方法
- 毎晩寝る前に、3行だけ「今日の気持ち日記」を書く
- 「こう感じた→なぜ?→本当にそう?」と自分に問いかける
- スマホのメモでも、紙のノートでもOK!好きな方で続けてみてください
続けていくうちに、**「感情に飲み込まれる前に気づける力」**が自然と育っていきます。
気持ちを書くだけで、自分の味方になれる。
これ、めちゃくちゃコスパのいいセルフケアです。
3. 頑張った自分を、意識してねぎらう
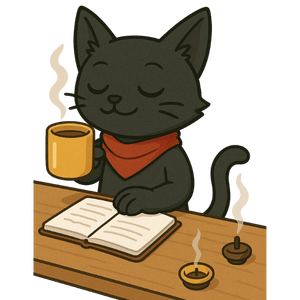
「今日もがんばったね」って、自分に言えてる?
HSP(繊細な気質)さんって、人に共感しすぎて疲れても、「まだまだ頑張らなきゃ」って無理しちゃうところがあるんですよね。
でもね、実はいちばんの回復法は、「自分をちゃんとねぎらうこと」だったりします。
「私は今日もよくやった」
そうやって自分を認めてあげるだけで、心のエネルギーがふっと戻ってくるんです。
僕が実践してるのは、こんな感じ。
- 子どもを寝かしつけたあとに、「今日の自分をねぎらう時間」を3分だけつくる
- 「今日も泣いた子に寄り添えたね」って、声に出して自分に言ってあげる
- お気に入りのアロマで深呼吸したり、温かいお茶をゆっくり飲んで五感から癒す
こういう時間って、一見地味なんだけど、めちゃくちゃ効くんです。
「ねぎらうこと」は、ただの自己満じゃありません。
それは、“明日の自分をいたわる準備”でもあるんです。
だから今日も、少しだけ立ち止まって、
「よくがんばったね」って、自分に優しく声をかけてあげてください。
体験談:私も「共感疲れ」でぐったりしてました
子どもが感情的にな「共感=抱え込むこと」じゃなくていいんだ
子どもが泣くたびに、一緒になって涙が出そうになる自分がいました。
「保育園で先生に注意された…」
そんな話を聞いただけで、まるで自分が叱られているような気持ちになってしまうんです。
家に帰っても、そのモヤモヤがなかなか晴れなくて。
夜になっても気分が沈んだまま…なんて日もありました。
でも、あるときから、**感情を整えるための“ちいさな習慣”**を意識するようにしたんです。
- 「これは子どもの感情」と、そっとつぶやく習慣
- その日感じたことをメモに書いて外に出す
- 1日1回は、「今日もよくやった」と自分をほめる
この3つを取り入れるだけで、少しずつ、感情の波に飲まれにくい自分になっていきました。
子どもの感情に共感するのは大切。
でも、共感=抱え込むことではないんですよね。
ちゃんと距離をとって、自分の心を守ってあげる。
それも立派な「やさしさ」だと、今では思えるようになりました。
よくある質問(Q&A)
- 共感しないと冷たい人に見えませんか?
-
共感と“抱え込み”は別物です。やさしさを保つためにも、距離感が大切なんです。
- 子どもがつらそうなとき、どうしても気になってしまう…
-
気にしてOK。でも、自分まで沈まないように「今は話を聞くことが自分にできること」と線を引きましょう。
- 毎日感情に飲まれて疲れてしまいます…
-
それは頑張っている証拠。自分の感情にも目を向けて、日々少しずつ“線引き”と“ねぎらい”を習慣にしてみてください。
まとめ:共感しすぎる自分を責めずに、やさしく整えていこう
HSPさんは、感受性の高さ=やさしさの証。
でも、そのやさしさを「自分にも向けること」がとても大切です。
- 感情の境界線を引く
- 気持ちをメモに書いて整理する
- 自分をねぎらう時間を持つ
この3つの習慣で、 「子どもを思いやりながら、自分も大切にする」子育てが叶います。
- 子どもの感情に反応したとき、「これは誰の感情?」と問いかけてみる
- 日記やスマホメモに“今日の気持ち”を3行書いてみる
- 寝る前に1分、「今日の自分」をねぎらってみる
共感はあなたの強み。 でも、それを“やさしさのまま”保つために。
まずは自分の心を、整える習慣を始めてみましょう。